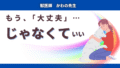はじめに:暖房をつけているのに寒そうに見える理由
冬の時期になると、室内をしっかり暖めているのに、
わんちゃんや猫ちゃんが「なんだか寒そう…?」と感じることはありませんか。
手足が冷たかったり、体をぎゅっと丸めて寝ていたりすると、
つい「部屋は暖かいのになぜだろう?」と心配になりますよね。
実は、室内が十分に暖かくても、
年齢を重ねた子や、持病がある子の場合は、
体の中が冷えやすいことがあります。
これは特別なことではなく、
体の変化によって起こりやすくなる「よくある現象」です。
シニア期の子が冷えを感じやすくなる理由
年齢とともに、わんちゃん・猫ちゃんの体にはさまざまな変化が起こります。
そのひとつが 筋肉量の減少 です。
● 筋肉は熱をつくる働きがある
筋肉は体温を保つための大切な組織。
しかし、シニア期になると徐々に筋肉量が減り、
体の中で熱をつくる力が弱くなっていきます。
そのため、
「部屋が暖かい=体も暖かい」
とは限らなくなるのです。
暖房が効いていても、
手足やお腹のあたりが冷たいまま ということが起こります。
病気による影響で体温が保ちにくくなることも
また、年齢だけでなく、体質や体の状態によっても
冷えを感じやすくなる子がいます。
ここでは一般的な例として、
血流の変化や代謝の低下 が起こると、
体温が安定しにくくなることがある、という点をお伝えします。
特に体の水分バランスは体温にも関係しています。
水分の偏りがあると、
手足やお腹まわりの冷えにつながることがある と言われています。
「暖かいのに寒そうだな…」と感じるときは、
そうした体の変化が背景にあることもあります。
こんな様子が見られたら、“冷え”の可能性も
難しく考える必要はありません。
日頃の様子から、少しだけ気をつけて見てみるだけで大丈夫です。
代表的なサインをまとめると──
- 手足や耳がひんやりしている
- 体を小さく丸めて寝る時間が増えた
- 以前よりも動きがゆっくりしている
- 食欲にムラがある
- 温かい場所を選んでじっとしている時間が増えた
これらは「冷えているのかな?」と
気づくきっかけになる様子です。
もちろん、これだけで何かを判断する必要はありません。
ただ、生活環境を整えるヒント にはなります。
今日からできる、体をあたためる工夫
体の中の冷えに気づいたら、
お家でできる簡単な対策がいくつかあります。
● ブランケットや湯たんぽを活用する
体の近くに柔らかい温もりを置いてあげると、
体の芯からじんわり温まりやすくなります。
● ベッドの位置を見直す
床はどうしても冷えやすい場所。
ベッドの位置を少し高くしたり、
風の通り道を避けてあげるだけでも違います。
● 体に触れる温度を意識する
空気の温度だけでなく、
「その子が触れている部分の温度」も大切です。
ふんわりした毛布や、
冷えにくい素材のマットを選んであげると、
より快適に過ごせます。
温めすぎにも注意が必要です
一方で、
「もっと暖かくした方がいいかな?」と頑張りすぎると、
今度は別の負担がかかることもあります。
ずっと同じ場所で温まり続けると、
水分が失われやすくなることもあり、
暑さがストレスになる場合もあります。
大切なのは、
“ほどよい温かさ” を保つこと。
触ったときに「気持ちいいな」と感じる程度が
ちょうど良い目安です。
毎日の“ちょっとした習慣”が、安心につながる
難しく考えなくて大丈夫。
1日に数回、そっと触れてみるだけで大きなサポートになります。
- 手足の温度
- お腹まわりの温もり
- 体のこわばりがないか
あなたの手のひらは、
その子の“日常の変化”に気づくための道具にもなります。
「今日も暖かく過ごせているかな?」
そんな気持ちで触れてあげるだけで、
その子の安心につながっていきます。
まとめ:あたたかさは、安心と快適さを守るために大切な要素
暖房が効いた部屋にいても、
わんちゃんや猫ちゃんの体の中まで
しっかり温まっているとは限りません。
シニア期の子、体がデリケートな子は、
環境のちょっとした変化に影響を受けやすいことがあります。
だからこそ──
- 周りの温度
- 体に触れる部分の温度
- 日頃のちょっとした変化
この3つをやさしく見守ってあげるだけで、
その子の暮らしはより快適になりやすくなります。
今日もどうか、
そっと触れて声をかけてあげてくださいね。
あなたの手のぬくもりは、
その子にとっていちばん安心できる温度だと、
私は思っています。